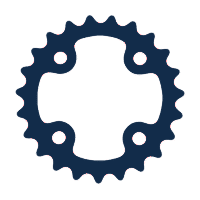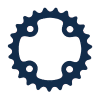インドに呼ばれる -ヒマラヤ編-
前回のコラム「インドに呼ばれる -都市編-」で、インドへ行くことになった成り行きや、首都デリーで受けた衝撃について書いたのだが、インドを旅した3ヶ月間のうち、実際都市や街に滞在していたのはわずか2週間ほどだった。
では、その他の時間いったいどこで何をしていたかというと、私たちは電気もガスも通っていない、ヒマラヤ山脈の奥地でテントを張っていた。そう、それが当時の私たちのインド渡航の、一番の目的だったのだ。

「インドへ行くのなら、ヒマラヤ山脈に登りたい。」エリオットは、インド行きが決まるや否や、第一声そう言った。
まるで今までに登山経験があるかのような発言だが、私も彼も登山に関しては、屋久島で日帰りトレッキングをしたことがあるくらいのまったくの初心者だった。またロンドン育ちのエリオットに至っては、山でキャンプさえもしたことがなかった。(それ以前に、イギリスには山がないのだが。)
私たちは初めての土地を旅するとき、どちらか一人が主導権を握ってリサーチをし、旅のプランを立てる。今回のヒマラヤ旅プランナーは、自然とエリオットになった。インドへ出発する1ヶ月前、ロンドンにいる彼から「ヒマラヤで必要なものリスト」がメールで送られてきた。軽量かつ保温性の高い寝袋、登山向きのバックパック、トレッキングシューズ、分厚い靴下・・などなど、揃えなければならないものがずらっと書かれてあった。
早速そのリストを片手にアウトドアショップへ足を運んだのだが、登山未経験の私にとって、数多くある商品の中からどんなタイプのものがヒマラヤ登山に適しているかなど検討がつくはずもなく、お店の人に相談しながらも、結局は値段とデザインを決め手に、必要な装備をさくさくと集めていった。
「標高はどれくらいの高さまで登るの? トレーニングとかなしに、いきなり行って大丈夫?」といった私の質問に対して、エリオットは、「標高は4000~5000mくらいまで登るかな? とにかく毎日エスカレーターは使わずに、階段をダッシュで上り下りしててよ。」と曖昧なゆるい返事が返ってきた。
ヒマラヤって、そんなものなのか?と少々不安に思いながらも、富士山より遥かに高い山など私の想像の域を完全に越えていたため、「してもしょうがない心配はしないほうがいい」という根拠のない信念に基づき、心配することをあきらめた。だけどその代わりに、私の前に立ちはだかるであろう険しく巨大な山に対し、「そう簡単には泣き言を言わない」と心に誓い、気合いだけしっかりと入れておいた。
そういった感じで、案外気楽な心持ちでいた私をよそに、事前に私より色んな知識と情報を得ていたエリオットが、心の中ではそれなりの不安を抱えていたことを知ったのは、だいぶ後になってからだ。

荷物をできる限り軽量化するため、インド全般のガイドブックや電子機器は持たず、コンパクトなトレッキングブックと必要最低限の衣服だけを常備して、ついにヒマラヤ山脈の麓まで到着した私たち。「ヒマラヤ山脈」と一言に聞くと、世界最高峰のエベレストのような、雪と氷河で覆われた真っ白の気高い姿を私はぼんやりと思い浮かべていた。
しかし全長2400kmにも及ぶ、私の目の前に広がる巨大なヒマラヤ山脈のほんの一部分は、その地域によって色も植物も気候もまったく違い、またそこに住む人々の暮らし方や宗教も多種多様だった。
ネパールとブータンの間にある、インド最北東部のシッキム州(かつてはシッキム王国という国だった)から登ったヒマラヤでは、人生で初めて高山病を体験した。激しい吐き気を感じながら、半歩前へ足を踏み出すのがやっとで、どうしてこんなしんどいことを自ら進んでやっているのだろう?と何度も自分に語りかけながらも、ただただ無心で前へと進んだ。数歩先が見えない深い霧と、意識が朦朧とする中で見たうねうねとした幹の巨大なシャクナゲの木は、まるでそんな私たちに襲いかかってくるようだった。

また、パキスタンとチベットに囲まれたラダック州のヒマラヤは、湿度の高いシッキム州とは真逆の砂漠系乾燥地帯だった。そこでトレッキングをしたザンスカール地方は、標高4000m~7000mに及ぶ高地にあるため、1年の半分以上が雪ですっぽりと覆われる。
極度の乾燥で指先は血が滲むほどひび割れ、朝起きるとテントに氷が張っているような厳しい環境だからこそ造られる赤や緑の山々や、限りなく澄み切った空気と青空は、私の心を完全な無の状態にした。
言葉や思考を必要としない、「生きる」自然の世界がそこには存在していた。

各地のヒマラヤで見た桁違いのスケールの大自然は圧巻の一言で、こんな場所が私のいる地球に存在してたのかというほど、感動の連続だった。今思い返しても、うっとりとしたため息が漏れてしまう。だけど、こういった知らない世界を目の当たりにしたときの感動よりも、さらに強く感じたことは、自分を取り囲むすべてのものに対する、「ありがたみ」だった。
そしてそれをもっとも体感したのが、ネパールとラダック州の中間に位置するヒマーチャルプラデーシュ州の山での2日間だった。この2日間、私たちは標高4000mを越える山奥で、文字どおり、遭難をした。
ヒマラヤでの二度の5日間トレッキングを終え、やっと山登りの楽しさが少しずつ分かり出した頃、私たちは新たに2人のメンバーを加え、さらなる山を歩いていた。この山は過去のトレッキング地とは違い、登山者のための道というよりも、山奥に暮らす村人が日々利用している小道を辿るようなルートだった。そのため何度か分かりずらい道に迷いながらも、村人に道を尋ねたり、地図を確認しながら順調に歩いていった。
私たちの常備していたトレッキングガイドブックには、山頂まで登ったあと同じ道を引き返すルートと、山頂からさらに奥へ進んで、北部のまだ見ぬ村へ縦断するルートとの2つのルートが載っていた。そのため、どちらのルートでも選べるようにと、今回の旅のための全装備(計15kgほど)を背中のバックパックと前のサブバックに詰め込んでいた。かつてないずっしりとした肩と膝にのしかかる重さに奮闘しながらも、自分たちのペースで着実に前へ進んでいる感覚に、満足感を覚えるようになっていた。
そうして3日後、私たちは無事山頂に到着した。頂上から先の山の尾根には、雪がまだたくさん残っていて驚いた。頂上にいたインド人登山グループは、このあと同じルートを引き返すという。
私たちは、山頂の野原でガイドブックを広げ、引き返すか先へ進むかを決める作戦会議をすることにした。次の村へ着くまでの2日間は、山小屋さえも何もないとのことだ。
2日間分の最低限の食料は常備してある。この先に広がる景色を見てみたい。そしてなにより、ガイドブックにこのルーは、“Moderate (中度)”と記されている。その事実が、私たちの気持ちを後押しした。そうして、私たちはほとんど迷うことなく先へ進むことを決め、すぐに誰もいない未開地へと歩き出した。
しかし、この決断を後悔するまでそう長くはかからないことを、この時の私たちはまだ知らなかった。

歩き進めるにつれ、残雪がさらに多くなっていることに気がついたのは、山頂から30分ほど歩いた頃だった。雪に隠れて小道が見えなかったのか、すでに道を外れてしまっていたのか、そもそも道らしき道など存在しなかったのかは、今となっては分からない。
山と川の地形から、向かっている方角が合っていることは確かだったが、ルートを逸れてしまっていることも確かだった。もう引き返したほうがいいんじゃないか?と心の中で思いながらも、なぜかそれを口には出すことができないまま、どんどん険しくなっていく道のりを必死に進んでいた。
切り傷を作りながら低木の茂みをかき分け、急勾配の崖を木にぶらさがりながら落下するように下り、底が見えない残雪の斜面を足場を作りながら横切った。全神経を歩くことだけに集中させていたせいか、頭の中はからっぽで、バックパックの重みも足の痛みも何も感じなかった。じわじわと少しずつ山が険しくなっていったこともあり、ふと我に返ったときにはもう、同じ道を引き返すことができないところまで来てしまっていた。
太陽はすでに傾き始め、皆の緊張と不安と恐怖心が濃くなっていくのを感じながら、私は弱音を吐かないようにすることがだけに精一杯で、前向きな言葉を一言も発することができなかった。あぁ自分は思っていたより弱いのだな、と普段は見えない、窮地に立たされたときの自分の本質を垣間見たような気がした。
何とかたどり着いた平地で、休む暇なくテントを張り、動物が夜中近寄ってこないよう大きな火を焚いた。少し歩いたところに水を補給できる川があったが、あまりの激しい濁流でとても近づけそうになかったので、私たちは雪を焚き火で溶かして水を作ることにした。雪には土や泥が混じっておりそのまま飲む事はできず、雪を鍋で溶かしたあと、Tシャツでその水をろ過し、半分にカットしたペットボトルに貯めるという地道な作業を何度も繰り返した。
今までこんな状況に陥ったことがないにもかかわらず、不思議と自分たちの限られた持ち物で対処する方法がぽんぽんと浮かんできたことには驚いた。「明日は目的の村へ辿り着けるはず。」と信じようとしながらも、やはり不安な気持ちは隠しきれず、黙々と焚き火であたためたカレーとご飯を頬張った。
その場所には、人間の生み出した文明が何もないようだった。目の前には7000m級の山々の影が月明かりで浮かび上がり、動物の遠吠えだけが聞こえる深い静寂に包まれていた。この世界に、まるで自分たちとこの壮大な自然しか存在していないような不思議な感覚に陥りながら、寝袋に包まった。

翌朝、日の出とともに自然と目が覚めた。
正しい方角に歩き続ければ、道は見失っていようとお昼過ぎには目的の村へ到着するだろうというのが、私たちの考えだった。夜中に動物がテントを襲ってくることは無事なかったが、岩場にまとめて隠しておいたチョコレートやナッツの非常食がまるまる跡形もなく消えているではないか。ということは、この日の残りの食料はチャパティが一人1枚ずつのみだ。その半分を大事に噛み締めながら食べ、落ち着く間もなくすぐに歩き始めた。
とにかく一刻も早く村へ続く道を見つけ出し、人のいる場所へたどり着きたいという思いだけで、ひたすら歩き続ける。しかしそんな願いとは裏腹に、道らしき小道が現れてもすぐに途切れ、路頭に迷うということを繰り返した。
無心で止まることなく10時間ほど歩き続け、ついには日が傾き始めてしまった。この不安定なぎりぎりの状態が今晩も、そしてまた明日も続くかと思うと、全員の焦りと恐怖心がピークに達し、エリオットと一人の友人は口論を始め、常に前向きだったあと一人も足の痛みを訴えて歩くスピードが極端に遅くなっていった。そして皆を繋ぎ止める言葉をかける余裕もなかった私は、「もうどうしたらいいんだ!」とただただ混乱した。
「もう、テントを張れる場所を探そう。」そう決めてから間もなく、数百メートル離れた山から、カゴのようなものを背負った人たちが走り降りてくるのが見えた。「人」だ!!
それを見た瞬間、私たちは大きく手を振りながら大声を出して彼らに駆け寄り、村までどうか連れ帰ってほしいと懇願した。インド人にすがられることはあっても、インド人にあれほどすがる機会は早々ない。
少しだけ英語が話せる一人の男性は、とびっきりの笑顔と明るい声で、「No problem! もうじきに日が暮れるから急ぎ足でいくよ!」と言い放ち、すぐに私たちを引き連れて山を駆け出した。もう全員空腹と疲労で動けないほどだったのに、その時は疲れも痛みも一切感じることなく、ものすごい速さで山を駆け下りるパワーが漲っていた。
あまりにも一瞬のうちに状況が逆転したため「あぁ、助かったのだ」と実感したのは、目的の村が見えてきた2時間後だった。村に着くや否や、村中の子供からおじいちゃんおばあちゃんまでが、なんだなんだと私たちの周りにぞろぞろ集まってきた。その山の中にある、私たちが夢にまで見た小さな小さな村は、泥まみれの突然の訪問者を、とってもあたたかく迎えた。人々の優しい表情を見て、思わず涙が出そうになった。

私たちをピンチから救い出してくれた男性とその奥さんは、山に薬草を摘みにきていて、その日はいつもより遅くまで山で働いていたらしい。その一瞬のタイミングを掴んだことを、心から感謝をした。
その夫婦は、そう広くはない家の一部屋を私たちに貸してくれ、定番のターリー(カレーとご飯とチャパティと野菜炒め)を振舞ってくれた。あれほど美味しかったカレーは今までにない。何杯もおかわりをし、美味しい!美味しい!と言って無我夢中になってご飯を手で頬張る私たちを、その夫婦は嬉しそうに、にこにこと眺めていた。
冷たい山水のシャワーで真っ黒になった体を洗い流すと、まるで生まれ変わった気分になり、ただただ笑みがこぼれた。インドに来てから、あったかいお湯のシャワーのありがたみは身にしみて感じていたけれど、この時は冷たい水のシャワーであっても、「蛇口をひねれば水が出る」ということに純粋に感動した。
その村で過ごした時間は、柔らかい幸せで溢れていた。心配することなど何もない。私たちは、「生きている」。
「死」を意識するということは、「生」を感じることなのだと、この長い長い2日間を通して初めて知った。
村を去って、山を下り、大きな街へ辿り着いたとき、私たちはその場に立ち尽くしてしまった。多くの人や車が忙しく道を行き交う様子は、まるで古代から現代に一気にタイムスリップしたようだった。お金を払えば、チョコレートだってジュースだって、何だってすぐに手に入る。だけど、その時食べたアイスクリームは、私たちの味覚を満足させたものの、心まで満たすことはなかった。
きっと、「生きている」ことで十分だったのだと思う。大げさではなく、あのときは本当にそうだった。
しかしその時の感覚は、今までどおりの日常に身をおいている今、そのままそっくりと鮮やかに思い出すことはもうできない。そして、またあの極限状態に自分を追い込んでみようとも、恐ろしくてとても思えない。
だけど、ふと気持ちが沈んだときや、不安を感じたときには、一度落ち着いて、自分の身のまわりを眺めてみる。そうすると、あの美しく厳しいヒマラヤの景色が、私の中によみがえってくる。
2013 / 8 / 1