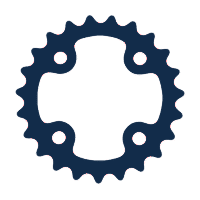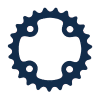インドに呼ばれる -都市編-
日本とイギリスをまたいで、エリオットと遠距離恋愛をしていた頃。せっかくなら一度、日本とイギリスの中間あたりにある、お互いがまだ行ったことのない国で待ち合わせをしようかという話になった。早速、壁に貼り付けてある世界地図を指でなぞり、日本とイギリスのおよそ真ん中付近を見てみると、1つの巨大な国が私たちの目にピタリと留まった。
“インド” 。そこは私もエリオットも、以前からなんとなく興味を抱いていた国だった。すぐにインド行きの航空券を調べてみると、値段はお手頃。フライト時間もそう長くない。そしてその時知ったのが、インドの国土面積は日本のなんと約9倍もあるということ。
そんな広大な国へ行くのなら、短期間じゃなくてある程度滞在したいね。どうせならその流れで、東南アジアに住む友人たちにも会いにいきたいね。といった感じで話をしているうちに、私たちのインド待ち合わせプランはあれよあれよと言う間に膨らんでいき、気がつくと往復ではなく片道の航空券を買っていた。
そうして私たちは、半年後にお互い仕事を辞めて、インドで再会することをすんなりと決めた。

エリオットとの再会とインドへの旅立ちを2週間後に控えたある休日。兵庫県にある横尾忠則現代美術館に立ち寄る機会があり、そこのミュージアムショップで一冊の本に出会った。
その名も、「インドへ」。
そのまんまのタイトルと、いかにもというヒンドゥー教の神様が描かれたカラフルな表紙。旅立ちがいよいよ近づき、インドモードがオンになっていた私は迷わずその本を購入した。本の内容は、横尾忠則さん自身のインド旅行記をコミカルかつスピリチュアルに書いたオムニバス形式のもので、70年代の話とはいえど、私のインド熱を駆り立てる興味深いストーリーとフレーズがいくつも載っていた。
その中でも特に気になった一文が、「人にはそれぞれ、インドへ行く時期が人生の中で必ず自然と訪れる。」というものだった。実際のところ、外国へ発つことに対してこんなにも胸がざわつくのは何年ぶりだろうというほど、私はこの旅立ちを心待ちにしていた。それはもちろん、彼との再会や仕事を辞めるという背景があったせいもあるだろう。だけど、半年前にインド行きの航空券を購入して以来、インドという国そのものにじわじわと惹かれていく感覚も、なぜだかはっきりと感じていた。
それは横尾さんの言葉を用いると、「インドに呼ばれている」と表現してもいいのかもしれない感覚だった。横尾忠則さんを始め、ビートルズや世界中の人々を強く魅了し続けるインド。私の周りにも、インドへ毎年のように行く友人や、長期滞在している知人がいる。いったいインドの何が、そんなにも人を惹きつけるのだろう?私の人生観も変わるくらいの何かがあるのだろうか?私はインドを好きになるのか、嫌いになるのか・・・ そう考えているうちに、私の頭の中はすっかりインド一色になっていた。
様々な人がそれぞれの形で語る、謎に満ちた「インド」という国を、とにかく自分の目で見て、実際どう感じるのかが楽しみでならなかった。

こういった色んな想いを募らせながら、ついに降り立ったインドの街は、普段使わない五感を強烈に刺激するもので溢れかえっていた。
気温は40℃。縦横無尽に人と牛が行き交う混み合った道路の脇には、つい顔をしかめてしまうほどの大量のゴミが山積みになっており、それを不健康そうな野良犬が食い漁っていた。しかしそれを見て感傷的になっている暇はなく、30秒おきに様々な切り口で物売りが声を掛けてくる。最初はできる限りの受け答えをしていたのだが、延々と鳴り響くクラクションと数歩ごとに変化する嗅いだこともないような悪臭に、聴覚と嗅覚を支配され、人と話すどころではなくなっていた。
そして一度一息つこうと食堂に入ったはいいが、そこで口にするカレーは舌が麻痺するほど激辛スパイスが効き、次第に汗と涙と鼻水が止まらなくなった。その全身から噴き出す水分を拭おうと、ふと自分の手を見てみると、何を触ったわけでもないのにぞっとするほど排気ガスと砂埃で真っ黒になっているのだった。
こんなにもたまらなく、「とにかく手を洗いたい!」と強く想ったことが、今までにあっただろうか?と、髪の毛一本落ちていない日本の清潔なトイレを頭に思い浮かべながら、その時に思った。

インドでは、今までの私の常識を覆す出来事がひっ切りなしに起こる。日常の中に、(特に関西人の私にとって)ツッコミどころが満載なのだ。その驚きに出くわすたび、自分の感覚や価値観が自然と変化し、結果的に人生観までも変えるほどのインパクトが、この国にあることは確かだった。
そんな目まぐるしい環境の中で、ごく普通に生活をしているインド人もまた、言うまでもなくインパクト大だ。道を聞けば、信じられないほど簡単にでまかせを言う。友達のように接してきたと思ったら、どこかへ勧誘しようとする。三輪タクシーでは、正規のメーターの値段で乗せてくれた人は1人しかなかった(それもしぶとい交渉ののち渋々)。
そういったインド人の外国人の私たちに対する対応に、最初は単純に腹が立っていたのだが、徐々に誰も彼も疑ってかかってしまう自分が悲しくなり、どう彼らと接したらいいのか分からなくなった。そしていったい彼らと私たちの何が違うのかと頭を抱えてしまった。
そんな困惑の最中、私たちはある一人の少年と出会った。

必要のない荷物の一部を日本へ送り返すため、私たちは首都デリー郊外の郵便局へ来ていた。そこは観光客など一人もいない生活感あふれる100%インド人の街で、市内とはまったく違った、どちらかというと貧しい雰囲気の下町だった。
インドの郵送方法はとても特殊で、どんな荷物でもまず仕立て屋に持って行き、白い布で梱包してもらわないといけない。布袋に入れても、布で包んでテープで貼ってもだめ。なぜか縫製してもらうというのが決まりだ。
その小包仕立て屋は、郵便局から徒歩5分の廃墟のような空間の一角にあった。仕立て屋といってもミシンが一台だけ置いてあり、文房具やスナックを売っている小さな売店といった感じだった。荷物をおじさんに渡すと、20分かかるとだけ告げられた。炎天下の中、周辺を散歩する気にもならなかったので、私たちは仕立て屋の前のコンクリートブロックに座って、ただただ出来上がりを待っていた。
暑さと疲れのせいかもしれない。その町はとても「グレー」に私の目に映った。人々は日々の生活のためにせっせと働き、それぞれの目の前のことで一杯のように見えた。彼らの毎日のささやかな楽しみって、何なんだろうなぁなどとぼんやり考えていると、砂埃の巻き上がる淀んだ空気の中、一人の少年がどこからともなくふらっと現れた。
少年は服とはいえないような汚れた布のまとい、おぼつかない足取りで私たちに近づき、なにかくれといった動作をした。その時私たちは食べ物も何も持っていなかったので、ごめん何も持ってないんだよと彼に告げると、またすぐどこかへゆっくりと立ち去っていった。
彼の目は焦点が合わず、幼い少年と思えないような生気のない無表情は、とてもとても暗かった。
インドの都市や観光地には、ストリートチルドレンが道端に溢れている。何十分も私たちのそばから離れようとしない子や、腕をぐいぐい引っ張ってくる子など、本当にたくさんの子供たちと出会い、時には話もした。
しかしその中でも一瞬だけ現れたその少年と、彼を取り巻く辺りの風景が、なぜか私の脳裏に焼き付いて離れなかった。10歳ほどのまだ幼い少年の目に、あれほどなんの希望も感じられなかったのはなんでだろう?彼がこれまでどんな日々を送ってきたのか、私に想像できるはずもない。だけどもし、私がこの空気の汚染された自然のない町で、周りの大人になんの希望も見出せず育ったなら、今どうなっていただろう?
色んな考えが私の頭の中を駆け巡り、もしあの少年が悪気なく人を騙すような大人になったとしても、それは仕方がないことなのではないだろうか、とさえ思った。逆にいうと、あの少年が他人を思いやれるような心優しい大人になることは、彼一人の力じゃほとんど無謀に近いことのように思えた。

郵便局で用事を済ませた帰り道、私は今まで腹を立てたインド人のことを思い返していた。彼らが育った環境と、私が育った環境には、雲泥の差がある。そんな彼らを短時間で理解し受け入れようと思っても、できるはずがないのは当たり前だ。そしてまた、彼らのバックグラウンドを何も知らないまま、ただ否定・批判するのはとても簡単で、と同時に愚かなことだと思い至った。
そんなスタンスでインドの人々に接してみると、それまでと違った彼らの一面が少し見えてくるような気がした。
2013 / 7 / 5