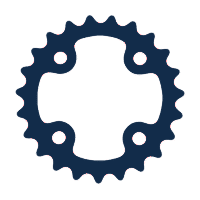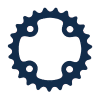ボランティアの謎
“マラウィ”という国の名前を私が初めて聞いたのは、今からたった1年半前。オーガニックドライフルーツやナッツを輸入しているお店で働いていたときだ。その知らざるマラウィという国からは、ミルキィで食べ応えのあるマカダミアナッツを輸入して販売していた。そのときの経験から、マラウィを着いたらマカダミアをたらふく食べられるぞ!と前々からかなり期待していたのだが、現在マラウィを旅して1ヶ月半。今のところ一度もマカダミアナッツが市場で売られているのを目にしていない。
旅をしていて知ったのが、マラウィで育てられるマカダミアナッツはとても高価な値段で取引されるため、その大半は海外へ輸出されているのだとか。
だけど山沿いの涼しい気候の地域では、民家の庭にほぼ自然に育っているマカダミアの木をよく見かけ、「このマカダミアナッツは市場で売ったりしないの?」と地元の人に聞いたら、「市場で売っても地元民には全然売れないから、自分たちで拾って食べるだけだよ。」という答えが返ってきた。その私たちの横では、小さな子供がまだ熟していない石のように硬いナッツをぼりぼりと食べている。
そしてその彼に、「マカダミアにはめちゃくちゃ栄養があって、マラウィのマカダミアは日本で買うとものすごく高いんだよ!」と説明すると、え!そうなの?!と驚き隠せない様子だった。
「大きな湖があって、美味しいマカダミアナッツを育てている!」とだけ知っていたマラウィという国。だけどこの国は、私とエリオットに沢山のメッセージと、リアルな「現実」を突きつけることになる。

国民の80%が電気のアクセスのない素朴な家に住んでいて、アフリカの中でも特に貧しいと言われるマラウィ。
そういうわけか、マラウィに入った途端、道の至るところに世界中からのNGOやAIDのボランティア団体の看板を見かけるようになった。そして自転車を漕いでいると、延々と続く質素な村の風景とは似つかわしくない、新品のToyota Land Cruserが度々私たちの横を通り過ぎていく。「ランクル買う余裕のある人も結構いるんや!」と一瞬思ったが、それは大きな勘違い。車体のドアには必ずといっていいほど、NGOかAIDのロゴが綺麗にペイントされてあった。
“ボランティア”とは、自分たちで解決できないような問題や境遇に立たされている人々や地域に、無償で手助けをし、彼らの生活や健康を維持することだと、ざっくりと自分の中で理解していた。だけど今、その“ボランティア”の形は確実に変わりつつあると、マラウィの旅を終えて実感している。

まず最初に強い疑問を感じたのは、マラウィよりも前、ナミビア北部でコンポストのボランティアをしていたときに遡る。
そこでとても良識のあるジンバブエ人の男性と知り合い、「コンポストやサスティナブルなプロジェクトに興味があるなら、ここに連絡してみたらいいよ。」と、象の糞を利用した巨大コンポストで大規模なオーガニックファームを経営している、ジンバブエの自然保護団体を紹介してもらった。もちろん興味を持った私とエリオットは、ぜひボランティアとして参加させてもらいたい!と、早速教えてもらったメールアドレスに連絡をした。
しかし数日後、送られてきた返信メールにはこう書かれてあった。「当施設にはボランティア参加者のための宿泊施設(プール付き)が完備されているので、テントで寝泊まりする必要はありません。食事も付いて、1日100ユーロ、1週間だと500ユーロになります。」といったような、義務的なメールだった。
1日1万円以上?!お手伝いするためにいくのに、お金が発生するの?というかそんな大金、いったいどこへいくの?色んな疑問がふつふつと沸き、そのメールに私たちが返信することはその後なかった。

そういえばケープタウンに住んでいたときも、はるばるアメリカやヨーロッパから、お金を支払ってボランティアに来ている人がよくいたなぁと思い出した。そのお金が何にどう使われているのかは別として、それでもどこかで誰かの助けになっているのなら、それは結果として、お互いにとって「いいこと」なのかなぁとも考えた。
だけど20~30年ほど前から活発的に、世界中のボランティアがこぞって集まるようになったマラウィでは、ボランティア団体がマラウィの人々へ与える影響が、長期的に見てとても大きく現れているような気がしてならなかった。
まず、マラウィの国境を越えてびっくりしたのが、そこらじゅうに人がいることだった。今まで通り過ぎてきたナミビア、ザンビア、ボツワナでは、数件の家が集まった集落があり、そこから数キロ(場所によっては数十キロ)誰一人としていない草むらが続き、また小さな集落がぽつんとあるといった感じだったのが、マラウィでは人のいない土地がほとんど見当たらない。
路上には頭に水の入ったバケツを乗せて歩く女性や、作物や家畜を自転車で運ぶ人でいっぱいで、ここなら周りに家もないし人目につかないだろうとお昼休憩に選んだ木陰でも、数分経つと何処からともなく現れた子供たちに気づけば囲まれている、といった具合。

そんな人口密度の高い土地で暮らす人々はというと、とっても穏やかで、通りすがりに皆んな笑顔であいさつしてくれる。子供は自転車に乗った私たちを見つけると、「アズング!アズング!(外国人、白人の意味)」と叫びながら両手を目一杯ふり、全速力で私たちの後を追いかけてくる。まるで私たちが、マラウィの子供に大人気のマスコット着ぐるみを着ているかのような、強烈なリアクションだ。
はじめのうちはそんな子供たちが可愛くって、その数十秒おきに聞こえる「アズング!ハロー!ハロー!(ハロー!は1回だけでなく、私たちが見えなくなるまでリピートされる※)」の声ひとつひとつに返答をしていたのだが、それが毎日5時間、6時間と続いてくると、さすがに普段の2倍疲れてしまった。
しかしそんな疲労困憊の私たちに、さらに追い討ちをかけるのが、半数以上の子供たちが口にする、「Give me Money!」の声だった。その言い方は、物乞いのような真に迫るものではない。アズングを見たときの合言葉のように、笑顔で無邪気に口にするのだ。

また、マラウィの人は基本的に正直で、商売っ気がない。市場で働く女性たちは、ほとんどと言っていいほど外国人である私たちに対しても初めからフェアーな値段で果物や野菜を売ってくれるし、もしぼったくろうとしていたとしても、うろたえる様子が分かりやすく目に見えるので、大概嘘を見抜けてしまう。
たとえ「Give me Money!」と攻撃的に口にする子供たちでも、私たちが彼らの前に自転車を止め、「Why should we give you money? Why do you want money?」などと面と向かって話すと、ほとんどの子供が黙り込み、恥ずかしそうにしながら素直に返答し、時には謝ったりする。
そんな性格のマラウィ人の子供たちに、なんでこんなにも「Give me Money」文化は浸透してしまったのか? ”外国人=お金持ち=お金ちょうだい!”というシンプルな発想から、その言葉を口にしていることは簡単に予想がつく。いくら私たちが自転車で旅をしていて、毎日テントで寝泊まり自炊生活で、自国に帰ったら確実にお金持ちの部類に入らないとしても、彼らにとっては、"お金持ち"の外国人だ。
じゃあ、”外国人=何かくれる!”という絶対的なイメージは、どこから来ているのか?
日々「Give me money!」の声を何時間も浴びながら、マラウィ全土をゆっくりと旅する中で、その理由が少しずつ分かってきた。

マラウィの首都リロングウェイに着くと、ボランティアをしにマラウィを訪れている外国人の多さに驚いた。その活動内容は、教育、農業、発電、栄養管理、医療と本当に様々だ。化粧ばっちりにハイヒール、金のネックレスにダボダボのズボンで、HIPHOPを夜通しキャンプサイトで流していた学生グループも、話をしてみると学校建設ボランティアのためにNYから来たというからたまげた。
観光半分、ボランティア半分の感覚で来ている人もいれば、困っている人の為になりたい、と心から思って来た人もいる。重要なのは、どんな支援をどんな方法で、誰にするかだと思う。
もし私とエリオットの母国である日本やイギリスの生活を基準にして、マラウィの人々の暮らしを考えてみたならば、それはそれは深刻な問題(とされること)でいっぱいだ。国民の平均収入が1日あたり100円~200円ほどに対して、市場で売られている野菜はさほど安くはないし(小さめのトマト4個で約20円)、メインの交通手段であるミニバスも50km区間だけで150円ほど。ほとんどの民家に電気は通っていないため、日が暮れると村内は真っ暗だ。また多くの子供は病気で親を早くに失い、教育や栄養が十分に行き届いていなかったりする。
ざっくりこういった事実だけ聞くと、彼らには外国からの助けが必要なように感じるかもしれない。だけど私とエリオットは、マラウィが"貧しい"とはあまり感じなかった。
確かに、私たちのようにお金を貯めれば海外旅行に行けたり、新品の服を買ったり、休日どこかへ出掛けたり、というような贅沢をすることは、彼らにとってとてもとても難しいのかもしれない。だけどマラウィの人々には、作物を育てる代々受け継がれた土地がある。赤土レンガで建てられた家がある。そしてどでかいマシェティ(大型の長刀)を持ってふらふら街を歩いていても何の問題にならないほどの、平和がある。
あるキャンプサイトで働いていた同世代のマラウィ人の女の子は言っていた、「We are poor, but we have peace.」穏やかなマラウィの人々の笑顔が、それをしっかりと物語っているように感じた。

では、外国からのボランティアがマラウィに出来ることは何なのか?それはマラウィの中でも、村によって、土地によって、全然違ってくるだろう。その本当の課題を自分の目で見極めることをせず、外国から立ち代わり入れ替わり人がやって来て、ボランティア団体に用意された場所で与えられた任務をすることは、なんだか不自然なような気がしてしょうがない。また、何かを「してあげる」「与える」という行為は、相手の手助けになると同時に、自分で何とかしようという相手のモチベーションを奪うことにも繋がる。
マラウィ湖で3週間、子供に絵を描くことを教えていたという50代のアメリカ人女性は、その学校に紙が少なく、スクールバックがなかったため、そのすべてを自腹で支給したと意気揚々と私たちに語った。
紙が足りている間はいいかもしれないけど、なくなったらまた誰かが支給するのだろうか?次の学年の子供たちは、スクールバックを持てるのだろうか?この先ずっと欠かさず与え続けることなんて、ほぼ不可能に近いんじゃないか、、、?
また、マラウィ南部で数日間お世話になったアメリカ人の老夫婦が率いるNGOでは、今年水害でマラウィ人の主食である白とうもろこしが壊滅したため、4000人の3ヶ月分に値する白とうもろこしをモザンビークから輸入し、村の人たちに提供していた。
かなりの大金がかかって大変だったと言っていたけれど、来年、再来年、またその翌年、
もし同じ災害が起こったら、果たしてまた同じように白とうもろこしを支給できるのだろうか、、、?
物を「与える」ことは、一番手っ取り早く、瞬時に人々を満足させることができる。だけどマラウィの人々に本当に必要なのは、その時限りの安心や幸せでも、ボランティアという名のビジネスでもなく、今後彼らが自分たちの土地で自ら生活し、健康に生きていくための実用性のある知識なんじゃないだろうか。

例えば、私とエリオットが持っている唯一の、マラウィの人にとって実用性があるだろうと思える知識といえば、地元の人にとってとても高価な化学肥料なしに、健康な作物を育てることができるコンポストの作り方や、貴重な木を伐採せずとも小枝で料理をすることができる、バケツと泥と砂のみで出来たロケットストーブの作り方だ。
コンポストの材料として最適のおがくずの山を家具職人の家の前で見掛けたときは、すぐに自転車を止め、おがくずは焼いて処分せずに、コンポストにしたら肥料になるよ!と、興味を示してくれた職人さんに作り方を説明して回った。
また色んな農家に立ち寄りもしたけれど、ほとんどの農家が(家族を養うほどの小規模でも)政府から補助金がでている化学肥料と農薬を使っていたことには、大きなショックを受けた。なんとかならないものだろうか、と悶々とするような現実があまりにも見えすぎて、なんとかしたくても何ともならないことに気分がずーんと落ちることもよくあった。
タンザニアの国境まで、あと60km。マラウィの旅ももう終盤。次マラウィへ来るときは、もっと自らの経験を兼ね備えて来たいな、なんてすでに先のことを考えていた矢先、意外な機会が私たちのところへ転がってきた。
その日私たちは、ある小さな村の中の入り組んだ場所にあるローカルキャンプサイト(といっても民家の敷地内にテントを張るのでほぼホームステイ)で一泊することにした。テントを張り終えてのんびりしていると、村の長老の世話役をしているというその家のお父さんが帰ってきた。
その家の片隅には、家族で食べるための小さな野菜畑があったので、野菜をどうやって育てているかという話題からコンポストの話へと発展し、色々と話をしていると、最近村でも化学肥料を使わず、コンポストで作物を育てようとしている、だけど肝心なコンポストの作り方を誰もきちんと知らない、明日よかったらそのコンポストの知識を会合で村の皆んなに話してくれないか?と、トントン拍子で翌日の村人へのコンポスト教室を開くことになった。
夜には長老が私たちを訪ね、私たちが話そうと思っている内容を彼に説明した。コンポストの実際の作り方を伝えることはもちろん大切だけれど、まず最初に理解を得るべきは、なぜコンポストなのか、ということだと私たちは思っていた。

会合は明日の午後12時、長老の家の前の木の下。今日の明日で、村の人は果たして集まるのか?と少し疑問に思いながら、いつもどおり夜8時にテントの中で横になっていると、数十メートル先から男性が何か叫んでいる声が聞こえてきた。真っ暗な静まり返った村に、男性の透る声だけが響く。
こんな夜遅くに何を大声で叫んでるねんと不審に思い、注意深く耳を澄ますと、同じフレーズを何度も繰り返していることに気付いた。そして「10」という単語だけを聞き取ることができ、「もしかして、明日10時に長老の家に集合~~!」っていう村内アナウンスじゃない?とエリオットに冗談を言って、そのまま就寝した。
翌日お父さんに、あの謎の大声の正体はなんだったか聞くと、本当に「明日10時に集合~!」の村内アナウンスだったので笑った。超アナログだ。「だけどなんで12時じゃなくて10時?」と聞くと、「もし12時って言ったら、皆んな15時に来るからね。」とお父さんは言った。公式村内アナウンスも、アフリカンタイムで成り立っているらしい。
12時半頃にお父さんと一緒に会合の場所へ行くと、20人ちょいくらいの男女が大きな木の下に集まっていた。そして話を始めた13時頃には倍くらいの人数になり、1時間くらいのトークを終える頃には60人ほどの村の人が私たちの話を興味深く聞いてくれた。
「私たちはNGOから来たわけでも何でもない、たまたま通りがかった農業に興味のある旅人だから、コンポストを作りなさいと指示してるわけじゃない。ただ私たちが信じてる有益な知識を、沢山の人とシェアしたいと思って今こうして話している。」とエリオットが言うと、皆んな大きくうなづいてくれた。

トークが終わると、「君たちがくれたアドバイスはこの村にとってとても大切なことだから、話してくれて感謝しているよ。だけどこの村には農業以外にも色々問題があって、学校には物資が足りず、先生たちの宿泊する場所がないんだ。」と長老は言い、私たちに長老の家の住所が書かれたメモを差し出した。支援をしてくれる人を探しているということなのだろう。内容は詳しく分からなかったが、誰か適任の人に出会ったら、このメモを渡すよとだけ言い、私たちはその村を後にした。
帰り道、村の中を自転車で走っていると、少し離れた丘の上に、とても立派な巨大な建物が見えた。マラウィの村ではめったにしないような、新築の建物だ。道行く人にあの建物は何かと聞いたら、新しい学校だよと教えてくれた。
あれ、長老、学校の問題がどうたらって言ってなかったっけ?どこからその学校建設の資金が支給されたのかは分からない。だけど今ある既存の学校も十分立派なレンガ造りの建物で、それぞれのクラスには先生も1人ずつおり、机と椅子も生徒一人ひとつずつきちんとあった。
必要なのは、立派な建物や物資じゃなくて、教育の中身じゃないの?長老。とひとこと言いたくなった。

今、私が思う、”ボランティア”とは。
それは単純なお金や物のやりとりではなく、具体的な知識やスキルを持った人が、それを本当に必要する土地で行う活動であってほしいと思う。ボランティアのこれからは、マラウィのこれから、と言ってもいいのかもしれない。
「Give me Money!」の子供たちの声が、「Give me Knowledge!」の声に変わったとき、私たちは喜んで自転車を漕ぐ足を止めるだろう。
2015 / 9 / 26