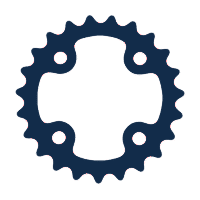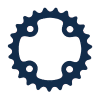屠殺と野生動物
ナミビアの旅が予想以上に長引いている。というよりも、ナミビアが予想以上に大きな国だった。
砂漠での未舗装道路800kmのあと、首都ウィンフックからアスファルトの720kmをせっせと北上。そしてついに縦断!と思ったら、次は横断が待っていた。ナミビアの地図をよく見ると、右上部分が不自然に突き出ている。今、まさにその部分を走っている。

ナミビアの見所スポットであるキャニオン、砂漠、サファリなどは、距離がそれぞれとても離れているため、ナミビアを旅するほとんどの人がテント付きの四駆車をレンタカーするか、あるいはツアーで旅をしている。その見所スポット以外の道中は、ひたすら砂漠だったり、ひたすら乾燥した草むらだったりするので、出会った自転車旅人はみんな、ナミビア旅の後半になると疲れが見え隠れしていた。
ブラジル人の友人は、「何もない所から何もない所へと移動するのはもういい加減疲れたから、あとはバスに乗るよ。」と言い放ち、カナダ人の友人は、「孤独すぎて、最後のほうは虫に話しかけてたよ。」と言っていた。
私はエリオットといつも一緒なので、それほどの孤独は感じないが、彼らが音を上げる気持ちはとてもよく分かる。数百キロとまっすぐに伸びる、風景の変動がない道を毎日何時間も漕いでいると、自分がどこにいるのか、いったい何をしているのか、ふと分からなくなるときがある。
しかしそんな思いをしてでも、時間をかけて自転車で旅を続ける理由の1つは、自転車旅ならでは巻き起こる、人との相互作用(インタラクティブ)だろう。
朝起きて、朝食のポリッジをガソリンストーブで作り、持ち物をすべてパッキングして、自転車を漕ぐ。というシンプルな日々のサイクルの中に、強いアクセントを加える出来事が、時々思いがけない瞬間に舞い込んでくるのだった。

ここ最近、いつものように自転車を漕いでいると、私たちの目の前に荷台が空っぽのトラックが急停車するということが、日を空けずに2度立て続けに起こった。最初に私たちに声をかけたのは、テリーというおじさんだ。
「どこまで行くんだ?乗っていくか?」断る理由もない私たちは、もちろんテリーのトラックの荷台に自転車を積み、車に乗り込んだ。
時速140kmで車はすいすいと道を飛ばし、私たちは3日間かけて向かうつもりだった隣町に、たったの2時間で到着してしまった。車の移動距離ってすごいよな、とこういう時に心底思う。
テリーは家畜農園を所有する傍ら、鉱山でダイナマイトを爆破する仕事をしている。私たちがたどり着いたその隣町は、昔から鉱山産業で栄えた町だった。そしてテリーはその日、50トンの爆薬を爆破させる鉱山をチェックしにいくと言ったので、時間だけはたんまりある私たちは、そのまま一緒に現場へ付いて行った。

直径数メートルの岩石を粉々にするどでかいマシーン。舞い上がる真っ白の砂埃と埃まみれの作業員。そして地面にぽっかり空いた巨大な空洞。
この鉱山は、コンクリートやレンガなど、様々なものに使われるらしい。テリーはそれぞれの機械の役割や爆薬の仕組みなど、丁寧に説明しながら案内してくれた。ここで見るすべてのものが、私たちが普段目にすることのないものだったが、そこで生み出されるものは、
私たちのごく身近なものに使用されていると思うと、何だか不思議だった。

そんな貴重な体験の数日後。「ヒッチハイクしてるわけでもないのに、車が自ら止まってくれることなんて、めったにないよな~」
などと思いながらいつもながら自転車を漕いでいると、前を走るエリオットの前に、トレーラーを取り付けてある一台の車が停車した。
え?もしかして?!と近づいていくと、そのもしかしてだった。キャンプサイト出発してたった1キロで、またも私たちは車に拾われた!
その日、私たちを乗せてくれたクリスというおじいさんは、そこから50km離れた僻地に家畜農園を持っていたが、先月その土地と家を売却して娘家族の住む町へ引っ越し、残った荷物を少しずつ運んでいるのだという。
飼っていた牛と羊のほとんどもすでに売ったのだが、まだ20頭ほどの牛は彼が所有していて、今日はその1頭を屠殺し、彼の家族の6ヶ月分の食肉として、引越し先へ持って帰るというのだ。そして私たちは自然な流れで、クリスの空っぽになった家に一晩泊まらせてもらうことになった。
屠殺、、、命を食べている以上、いつか実際にこの目で見るべきだと思ってはいたけれど、
まさかこのタイミングでそのときが来るとは。助手席にはさりげなく、
だけど強い存在感を放つ大きなライフルがエリオットの横に乗っていた。
クリスは旧農家に到着するとすぐに、普段牛の世話をしている男性の名を大声で呼んだ。
しばらくすると、ぼろぼろの作業着を着た黒人男性が一人近寄ってきて、クリスの指示するままに牛を探しに行った
。彼らはアフリカーンス語で会話しているためその内容は理解できないが、クリスのその男性に対する態度は、
私たちに対するフレンドリーなものとは明らかに違っていた。

牛たちが農園内に戻ってくると、私たちは屠殺を手伝ってくれるという男性たちを隣の農園までクリスと一緒に迎えにいった。なんでも、大きな牛は一頭450kgの巨体。その巨大な牛を打ち抜いたあと、トラックの荷台に手作業で載せなければならないため、そりゃあ人手がいる。
隣農園で5人の男性を荷台に乗せ、クリス農園に戻ると、クリスはそのまま牛たちが放牧されているゲートの中へと車を走らせた。え、もうその瞬間が来るの?と、心の準備ができていない私の心臓は急にばくばく鳴り出した。
車が牛たちに囲まれるように停車すると同時に、クリスは助手席のライフルを車内からさっと取り出し、銃を構えるとすぐに発砲した。たいして鳴り響くでもない、乾いた銃声音のあと、一頭の牛の前足ががくっと折れ、大きな体がそのまま地面にドンッと倒れた。あまりに一瞬の出来事で、目をふさぐ間もなかった。
無機質なライフルのたった一撃で、ひとつの命がこんなにあっけなく失われるのかと、ただただ唖然とするばかりだった。

なにより胸がぎゅうっと締め付けられたのが、クリスがライフルを構えてから牛が動かなくなるまでの数分間、周りにいる牛たちが周囲の音が聞こえなくなるほどの大音量で鳴き続けていたことだ。かつて聞いたことがない異様な牛たちの鳴き声は、まるで悲鳴のようで聞くに堪えなかった。牛たちは、仲間が殺されたことを理解している。そうはっきり体感した。
そんな中、男性たちは慣れた手つきで素早く牛の喉をナイフで切って血を抜き、トラックの荷台にその牛を引きずり乗せようとしていた。成熟した450kgの牛は、男性5人でもなかなか持ち上げることができず、私とエリオットも一緒になって牛の足を引っ張った。なんと表現したらいいか分からない色んな感情が込み上げてきて、この時の私はかなり険しい表情をしていたと思う。

その後の作業は、とても手慣れたものだった。牛の両足首に碇のようなものを突き刺して地面から釣り上げ、皮を剥ぎ、脂肪を切り、内臓を取り出す。私たちは、もちろんクリスもその解体作業に加わるものだと思っていたが、彼は一切手を血に染めず、横から指示をするだけだった。2時間半ほどの重労働のあと、牛はその姿形を完全に変えていた。
解体の一部始終を間近で見学させてもらったが、意外とグロテスクに感じることも感情的になることもなく、私たちは興味深くその作業を冷静に観察した。屠殺現場を見てからベジタリアンになったなんて話をよく耳にするけれど、そんなことが起こる気配はまったくなかった。

私自身、普段スーパーマーケットでお肉を買って自分で調理することはほとんどないのだが、旅中や人に招かれたときなど選択肢がないときは、抵抗なくお肉を食べる。そして、食べるときは生きたその動物の姿と、どこからそのお肉がやってきたのかを自然と想像する。
食べ物なら野菜でも果物でもなんでもそうだろうけど、ありがたみを持って食べることが何より大事なことだと思う。ありがたみを感じたら、食べ物を残したり、無駄にすることはできないはずだ。この屠殺見学体験は、その気持ちをさらに強くさせることとなった。

この不思議な逆ヒッチハイク体験の数日前、私たちは家畜の動物たちとは対照的な、野生動物がわんさかいる国立公園へ初めてのサファリへ出かけていた。野生動物とはいっても、だだっ広い国立公園のゲート内に保護されているため、半野生動物だよなぁと、放し飼い巨大動物園に行くような気持ちでいたのだが、実際は違った。
何十頭もの群れをなして移動するシマウマや、親子で草を食べるキリン。今まで見たことがあった動物園の動物たちとはまったく違った生命力を感じた。

なかでも特に感動したのが、ゾウの群れだ。小さな水場に、森から砂埃をあげて20頭ものゾウが列をなして登場し、器用に長い鼻を使って水をたっぷり飲んだあと、喜びを分かち合うように水浴びをしていた。
まさに「生きてる」という迫力がひしひしと伝わってきて、素直にとても感動した。

私たちの生きる社会は、この圧倒的なワイルドライフや日頃食べている動物たちの生から、どんどんかけ離れた方向へ向かっている。だけど人間も動物も虫も植物もすべて、やっぱり自然の一部で、サイクルとして繋がっていることを忘れてしまってはいけない。ワイルドライフがまだまだ身近にあるアフリカは、そのことを常に感じさせてくれる。
2015 / 7 / 2